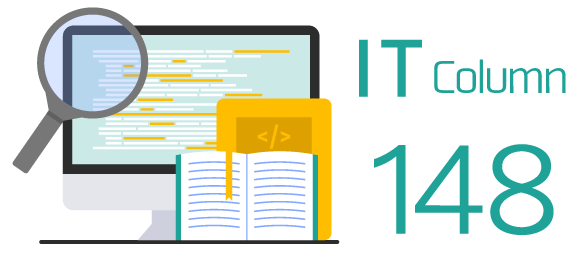ITコラム
親しみやすさが問い合わせにつながる!士業のホームページ制作のポイント
普段あまりユーザーにとって馴染みのない士業にとって、ホームページは名刺代わりにもなる重要なツールです。無形商材であるため、この事務所なら安心して相談できそうと感じられるホームページを制作すれば、集客やお問い合わせ数の増加が期待できます。この記事では、士業のホームページの特徴や制作する際のポイントをご紹介します。
◎士業のホームページの特徴
士業のホームページでは、ユーザーが親しみやすさや信頼感を感じられるデザインにできるかが大きなポイントです。訪問するユーザーは、自分だけでは解決できない問題を抱えているケースが多いのではないでしょうか。士業関連の事務所は、専門性の高い内容を扱っているほか、日常的な関わりが少ないため、敷居が高いと感じるユーザーも少なくありません。情報過多でテキストばかりのホームページでは、ユーザーがわかりにくいと感じ、離脱してしまう恐れがあります。お問い合わせにつながる士業のホームページを制作するためには、専門用語を避け、ユーザーが必要としている情報をわかりやすく伝えることが大切です。
一般的に、士業のホームページには、事務所概要や代表挨拶、業務内容、料金案内、相談受付用のフォームなどが掲載されます。ユーザーは、自分の住んでいるエリアで士業を探している場合も多いため、事務所概要には所在地や連絡先、アクセスをわかりやすく記載しましょう。従業員数や資本金、取引銀行、主要取引先といった詳細があるとユーザーはより信頼感を持ちやすくなります。歴史のある士業の場合は、沿革や実績も載せておくとアピールポイントになるでしょう。
士業のホームページでは、料金を掲載しないケースも多くありますが、価格に関する記載がないと「高そうだから」とお問い合わせをためらってしまうかもしれません。視覚的にわかりやすい料金表などを用いて、費用や計算の仕組みを記載するとよいでしょう。金額を示すのが難しい場合は、着手金や報酬金など、どのようなサービスに対して費用が発生するのかを記載すると、ユーザーに対して誠意を示した親切なホームページになります。
ほかにも、笑顔の写真やイラストを多く用いたホームページを制作すれば、士業の堅いイメージを払拭できます。トップページにユーザーが親しみを感じやすい写真やイラストを掲載するとともに、寄り添って問題を解決する姿勢や、納得できる結果に導く姿勢の伝わるキャッチコピーを掲載するのがおすすめです。業務内容は一般のユーザーでも理解しやすい言葉で説明し、よくある質問や相談までの流れも掲載しておくと、信頼を獲得できる親切なコンテンツといえるでしょう。

◎士業のホームページ制作のポイント
士業のホームページは、士業ごとの広告ルールや法律に従いながら、親しみやすくわかりやすい表現を用いてつくる必要があります。情報が整理されたホームページは、ユーザーに安心感を与え、士業への問い合わせにつながります。
○景品表示法や各士業の広告ルールに注意する
士業のホームページを制作する際は、景品表示法に注意する必要があります。景品表示法とは、商品やサービスの品質・内容・価格などに関する表示を偽ったり、過大な景品類の提供を禁止し、消費者の利益を守るための法律です。景品表示法では、「必ず」といった断定的な表現で他社よりも自社が優れていると誤解させる表示や、専門用語を多用してユーザーがサービス内容を正しく理解できないようにする表示を禁止しています。また、弁護士の場合は日本弁護士連合会によって業務広告に関する指針が定められているなど、景品表示法以外に独自の広告ルールが定められている場合もあります。専門性が非常に高い士業のホームページは、誤解を招くような表示を行うと法的責任を問われるトラブルにも発展しかねないため、注意が必要です。法律違反の内容によっては、懲役や罰金が科せられる場合や、事業が継続できなくなる恐れもあります。士業のホームページを制作する際は、掲載する内容が景品表示法や専門分野の広告ルールに違反していないか、十分精査を行ってから公開するようにしましょう。
○親しみやすいデザインにする
一般的に堅いイメージのある士業のホームページは、ユーザーに親しみやすいと感じてもらえるデザインに仕上げることが大きなポイントです。馴染みの少ない士業への依頼を難しく感じたり、頼りたいけれど気軽に頼みづらかったりと不安を感じているユーザーも少なくありません。そのため、トップページに先生の笑顔の写真を使用すると安心感につながりやすくなります。写真の明るさやクオリティも印象を大きく左右するため、撮影はプロに依頼するのがおすすめです。写真の掲載が難しい場合は、親しみやすさを与えやすいイラスト調のデザインも効果的です。イラストや明るい配色を使用すると、士業は難しそうというユーザーの先入観を緩和できます。士業のホームページに掲載するメッセージは、堅苦しい表現や難しい言葉は避けて寄り添う姿勢を見せましょう。先生のプロフィールや趣味を掲載したり、丸みのあるフォントを利用したりする工夫も、親しみやすさを与えるうえで大切です。
○専門用語を避けわかりやすく記載する
法律を扱う士業といっても、司法書士や行政書士、社会保険労務士など、職種によって業務範囲は異なります。それぞれ専門的な分野のため、一般の人にとって士業の業務範囲を区別するのは簡単ではありません。士業のホームページを制作する際は、自社で扱える業務内容を明確にし、わかりやすく記載するのがポイントです。業務内容は会計や相続、会社設立、遺言状の作成など、業務ごとにページを分けて作成すると、ユーザーは必要な情報にアクセスしやすくなります。士業のホームページでは、単に業務内容を説明するだけでなく、依頼することで避けられるトラブルの例や、なぜ専門家に依頼すべきなのかを記載しましょう。自力で問題を解決するよりも士業に依頼するメリットをユーザーに理解してもらえると、問い合わせにつながりやすくなります。また、ひとつの分野に特化している士業の場合、トップページや業務内容の目立つ位置に相続専門などと記載しておくと、ターゲットユーザーの興味をひきやすくなります。
○事例やよくある質問を掲載する
士業のホームページ制作の際、事例として過去の実績を掲載しておくと、ユーザーの安心感や信頼感につながります。ユーザーによっては、士業に相談する内容について迷っているケースもあるでしょう。ホームページでさまざまな状況の事例を紹介しておくと、ほかのユーザーの相談背景や士業に依頼して生じた成果を確認できます。似た状況の事例があれば、依頼後のイメージがしやすく、問い合わせにもつながりやすくなります。実績の豊富さをアピールできるため、事例はできるだけ幅広い相談内容や業界をカバーするようにしましょう。また、事例に加えてよくある質問を掲載しておくと、はじめて士業を探しているユーザーに役立つ情報を提供できます。よくある質問があることで、ユーザーの疑問がすばやく解決され、申し込みへのハードル低下やお問い合わせ件数の増加につながります。
○相談の流れをわかりやすくする
ホームページを見て依頼してみたいと思ったものの、相談の流れがわからず不安に思うユーザーは少なくありません。ユーザーの不安を払拭するためにも相談から依頼までの流れをわかりやすく記載しておくなら、親切で顧客満足度の高いホームページに仕上がります。まずは、お問い合わせフォームから相談依頼を行い日程を調整するといった流れを掲載します。さらに、事務所を訪れる際に必要となる書類や準備しておいてほしいこと、実際の相談での様子などを簡潔に記載しましょう。専門分野外で受けられない相談や、内容によって別の専門分野の士業への案内が必要となるケースも記載しておくと親切です。また、依頼前に見積りをつくり、ユーザーが納得したうえで契約を開始することも明記します。士業への依頼は高額となるほか、予算の目途を立てにくいユーザーが多いのも事実です。ユーザーが安心して問い合わせを行えるように、無料で行える相談範囲またはどの時点から費用が発生するかの情報を明記することも大切です。
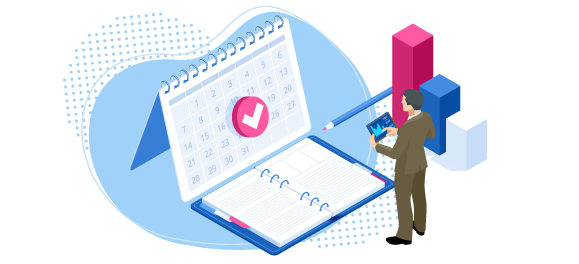
◎士業のホームページ制作を成功に導くSEO対策
ホームページは、普段の生活で士業との関わりが少ないユーザーにとって名刺代わりとなり、お問い合わせを判断する大きな要素でもあります。ホームページは存在しているものの何ヶ月も更新されていなかったり、専門用語ばかりが並んでいて堅苦しい印象があったりすると、ユーザーの不安要素が生まれてしまいます。また、士業のホームページは、制作して終わりではなく定期的な更新が大切です。
士業のホームページでは、SEO対策を行い、ユーザーに役立つ良質なコンテンツを継続的に発信しましょう。ユーザーは、自分の住んでいる場所などエリア名を特定して士業を探していることが多くあります。そのため士業のホームページ制作をする場合は、事務所のエリア名をホームページに盛り込んだり、エリア名をキーワードとしたコンテンツを導入するとSEO対策として効果的です。自分にあった弁護士の選び方や士業の無料相談をうまく活用する方法、専門用語の解説といったコンテンツは、ユーザーに有益と感じてもらいやすい情報です。需要の多いキーワードを用いて有益な情報を発信すると、ユーザーがGoogleなどで士業を検索した際に上位表示されやすいホームページに仕上がります。検索結果での上位表示は、問い合わせ数や契約数の増加に非常に効果的です。さらに、先生の執筆した書籍や論文がテレビや雑誌で取り上げられた際は、その内容を掲載するのもおすすめです。
現在は、スマートフォンで士業のホームページを見ているユーザーが大半を占めます。そこで、ユーザーに価値を与えるコンテンツ制作のほかにレスポンシブデザインへの対応もSEO対策として重要です。レスポンシブデザインとは、ユーザーの利用するデバイスに合わせて画面のレイアウトを自動で最適化する手法です。レスポンシブデザインへの対応を行うことで、スマホでの閲覧時にテキストやメニュー表示がわかりにくいという理由で、ユーザーがホームページから離脱するのを防げます。
近年は、SNSを活用する士業も増えています。拡散力の高いInstagramやTikTok、YouTubeなどを活用して自身の専門知識を発信するなら、多くのユーザーへのリーチが可能です。SNSを利用して、普段接点のないユーザーとのコミュニケーションが生まれ、親しみを持ってもらいやすいという効果も期待できるでしょう。SNSで認知度を高め、集めた見込み客をホームページに誘導して業務の詳細を提供するという導線がつくれれば、より効率的な集客が実現できます。
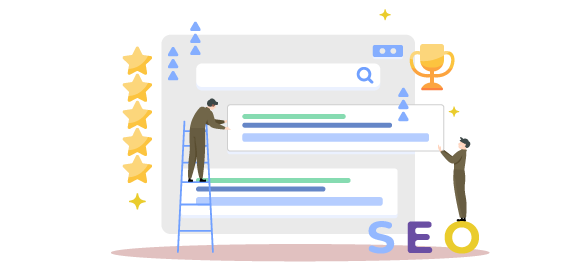
◎YTC・PLUSのホームページ制作
士業のホームページ制作では、ユーザーが親しみや信頼感を感じられるデザインに仕上げることが重要です。YTC・PLUSのホームページ制作は、カスタマイズの自由度が高いため、事務所の特徴や強み、雰囲気が伝わるホームページに仕上がります。私たちは、何よりもお客さまとのコミュニケーションを大切にしており、提案段階から対面でのヒアリングを行っています。ディレクター・デザイナー・ITエンジニアといった各分野の専門家が在籍しており、お客さまの予算や目的に合わせたホームページ制作が可能です。プロのカメラマンも在籍しているため、ホームページに掲載するスタッフの写真や事務所の撮影など、一貫してお任せいただけます。
ホームページは制作後の継続的な更新が大切です。士業の事務所は少数精鋭であることも多く、業務の合間を縫って更新作業を行うことも少なくないため、シンプルで使いやすいサイト設計が求められます。YTC・PLUSのホームページは、操作性に優れており、Wordやブログで文書を作成する感覚で更新できるのが特徴です。制作から運営までを一貫してお任せいただけるため、安心してご利用いただけるだけでなく、本来の業務に専念できます。

◎まとめ
士業のホームページ制作では、ユーザーが親しみを感じられるデザインやわかりやすい動線設計が重要です。実績のある制作会社に依頼することで、専門分野特有の表現や法的注意点にも的確に対応できます。当社では、制作だけでなく運用面も含めて、安心してお任せいただけるサポート体制を整えております。士業のホームページ制作は、YTC・PLUSまでお気軽にお問い合わせください。